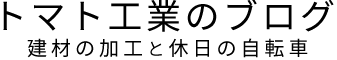【門外不出!!】工場の改善提案が劇的に出やすくなる法則
さてみなさまこんいちは。
まぶちでございますよ。
うちの会社、社員は20名ほどなんですが、2023年には、改善提案が年間600個も出てます。
なぜこんなにでるんだって話なんですが、
そもそもこれを3年くらい続けると、前の原型をとどめてないくらいの状態になるんですが、
それはなぜかって話をしたいと思います。
理論・法則が大事。
私、小学生のとき、剣道をやっとりまして、
理由が
親戚から電話かかってきて、
いとこ(女子)の防具があまったからやらない?
って聞いてきたことが理由なんですが、
あんな高そうな防具が、使えるなら、そんなチャンスないわ!!
ってことで、
多分ビーチフラッグくらい飛びついたんでしょうね。
うちの親が。
で、私がその少年団に入ることになりました。
肝心の防具なんですが、
まさかの
赤胴
でした。
ピッカピカの赤胴だったんですが、
死ぬほど弱くて、常時2軍でございました。
どんなバツゲームだよ。
で、その2軍なんですが、
先生が、多分どっかの保護者的な感じの人だったんでしょうね。
ムッチャクチャな教え方をしてまして
我々氷河期世代ならわかると想うんですが、
団塊世代特有の昭和的な教育術です。
男塾みたいな。

こちとら、小学生なのに、全力で体当たりをしてきて、
後ろにひっくり返って後頭部を強打するという
今なら完全にムショ送りのそれだったんですよ。
で、顔が真っ赤で、
赤鬼
と呼ばれていました。
剣道って、鍔迫り合いで、相手と対峙するんですが、
その時、酒の匂いがきつかったのを今でも覚えてます。
やたら練習時間が長く拷問みたいで、
量子くらい脚がもつれる。
当時の算数の公式は1mmも覚えてないんですが。
毎回、練習が終わるとみんなで、
酒クセェ。
今日はキツかったな。酒が。
というのが我々2軍の選手の共通感想でございましたね。
我々は体育館の上でひっくり返される。
ただそれだけの練習でございました。
毎回、苦痛でたまりませんでした。
昭和式技術論
昭和式技術論って、その人個人の成功体験
なんなら一切成功してないにも関わらず、自分がそう思う。
というレベルをひたすら強要してくる形の教育だったんですよね。
で、当時の剣道の教え方ってのは、
竹刀を後ろの背中の中央にあてて振れ。
って言われてまして、
そうすれば、力がついて早くなる。
っていうゲシュタルトくらい崩壊してる理論でした。
で、私も素直さだけが取り柄じゃないですか、
素直さ取ったらもはや、ジブリのない、ジブリ記念館みたいなものじゃないですか。
で、試合でもそれをやろうとしましたよね。
で、ただでさえ遅っそい打突が、
背中まで到達するうちに、相手から面を当てられるんですよ。
まるで、時代劇のやられ役じゃないですか。
負けに負けて、
小学生時代を通じてまぐれの胴を一本とっただけ。
赤胴なのに、死ぬほど弱いという、
ジブラさんの公開処刑もびっくりな圧倒的な弱さでした。
中学の体験
中学生になると、
我々弱小中学校、武儀中学校では、部活を3つからしか選べませんでした。
なにせ、町民が4,000人しかいないのでね。人口的に行ったら村なんですよ。
野球
バレー
剣道
20年前の吉野屋かっていうほどのメニュー数だったんですが、
野球はだめ、
バレーはもっとだめ。
というわけで消去法で剣道をやることに。
先生との出会い
そこには山田先生という体格のよい先生がいました。
とても素早そうには視えなかったんですが、打突がとてつもなく速い先生でした。
山田先生は、私にたった一つのことを教えてくれました。
“まぶちよ、背中まで到達してたら遅くなるだろ、
打突幅は5cmくらいに短くしろヨ。とにかく短くだ。
で、両手で雑巾を絞るように、
また前に飛び出るのと一緒にやればいいンダヨ。”
と言われたんです。
たったこれだけ。
しかしそこから私の剣道人生は一変しました。
打突は、50cmから5cmに、前に飛び出るタイミングと、雑巾を絞る動きの相乗効果で、
打突がめちゃくちゃ早くなったんです。
相手からすると、前に突っ込んでくる前進力と、
両手を絞る動きと、最短の振り幅によって打突スピードがめちゃくちゃ早く視えたんだと思います。
速くなれば、それは当たるということ。
私はその”突き”のような面をとにかく毎日練習することにしました。
来る日も来る日も、それだけを磨き続けました。
技はたったそれだけ。
なにしろ、小学時代は最も才能のない剣士だったからです。
高速打突
薩摩必殺示現流のように、前に向かう高速打突。
技はそれしかないので、相手に見切られたらもう終わりです。
この技しかなかったのですが、それのみを磨き続けた結果どうなったか。
2年のときには、上級生に混じって次鋒になりました。
そして3年生のときは、大将をつとめることができました。
最弱だった男がです。
県大会では1回戦敗退レベルなので、まったく才能のカケラもなかったのですが、
才能ある剣士に比べたら取るに足りない剣士でした。
しかし、自分比較では、爆発的に伸びたのです。
その山田先生の理論によって。
最後の試合は、富加のB&G体育館で行われました。
弱小チームであった我々が、関市や美濃市の学校と戦って3回戦まで進むことができました。
だれにもフォーカスされませんでしたが、私にはそれが一生の宝物です。
それまで、体育館の氷のように冷たい床に頭をぶつけてしか涙を流せなかったのが、
仲間と一緒に涙を流すことができるようになったのです。
理論は人を変え、そしてその人を幸せにする。
つまるところ、この体験が私の未来を変えてくれました。
打突を早くするポイントは、
①距離を短くする。
②動作を同時に行う。
③動作を両手で行う。
というたった3つの動作になります。
以降、これをとりまとめ、わずか6つの動作原則にまとめていくことで、
超効率、高速を自分自身で考えることができるようにしました。
これがトマト工業の動作経済の原点です。
もしかすると、いろんな職場では、昔の私みたいに、背中に一旦竹刀をあてて、
命の限り振り下ろす。
と言った、とんでもなく大変だが、非常に効率が悪い仕事の仕方をしているのかもしれない。
私はそう思いました。
動作経済の原則
たとえ才能が1mmもなかったとしても、原理原則を習得することで、
とんでもなく早く、効率的に、そして楽に動作が行えます。
動作経済、これが全社員が覚えるべき、動作効率化の原理原則です。
①動作の距離を短くする。
②動作を同時に行う。
③動作を両手で行う。
④動作は重力を使う。
⑤動作は道具を使う。
⑥動作は色を使う。
現場で困り事があるのであれば、この切り口で考えられないかをまず考えるわけです。
というわけで、
次からは、実践案について解説していきたいと思います。