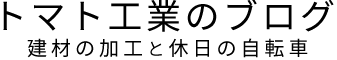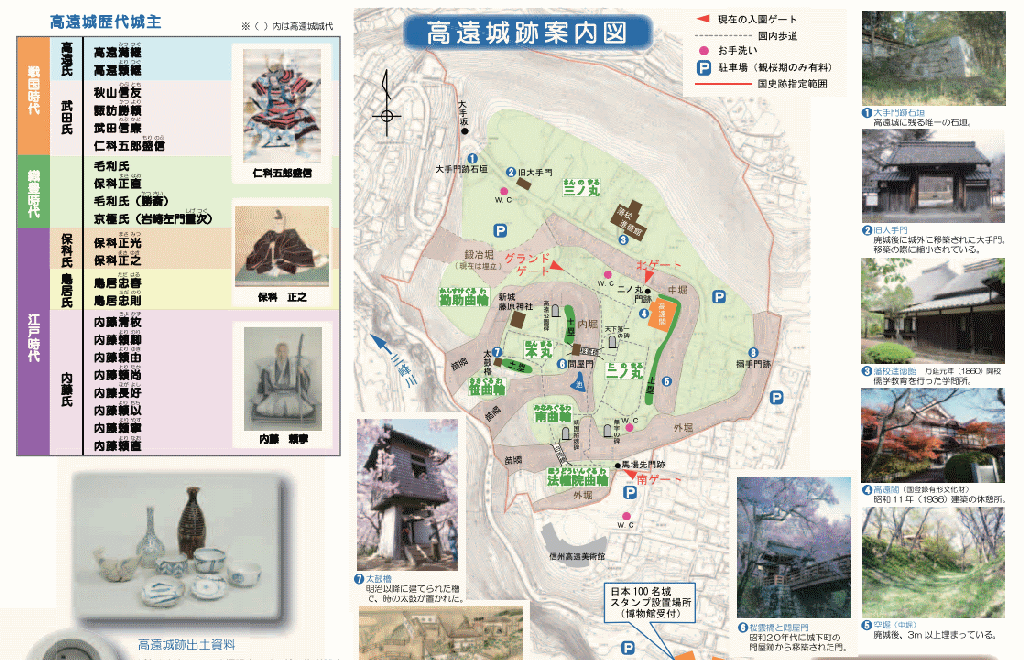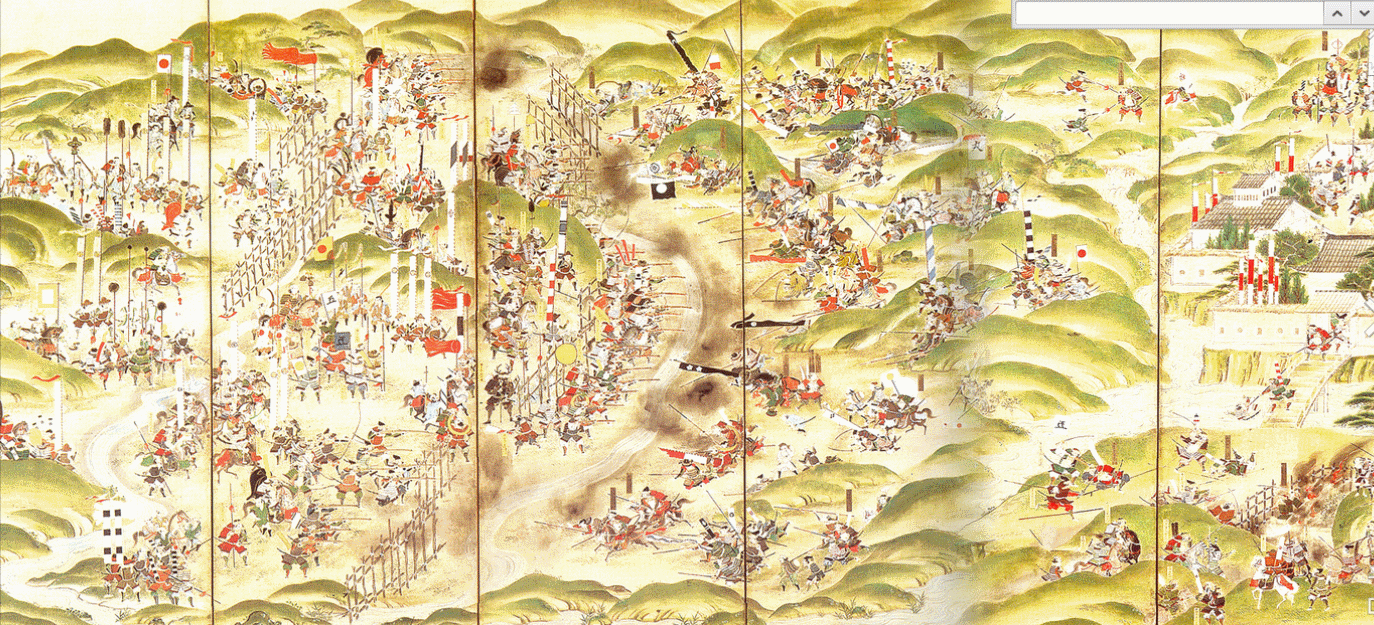信州高遠城跡に行こう!桜まつり編・古城探検第35弾・第1回
さて、皆様お元気でしょうか?
久しぶりの古城探検・今回は趣向を変えまして
華やかな平山城、信州は高遠に行ってまいりました。
いつも薄暗い山中を徘徊して泥太郎になって帰ってきてますのでね。
たまには”華”も必要でしょう。
この私も武田信玄研究家としての側面も
もつわけじゃないですか?
というわけでもはや聖地と化した高遠、いや高遠城について行かないわけにも行かないわけです。
とは言えかなりの遠距離であり、家族を誘って小旅行という形で行く必要があるのでございます。
高遠といえば桜で有名であります。
桜まつり
そのため桜まつりに行こうよ!
SAKURAMATURI
なんという響きでしょう。
ということで嫁さんたちをこの信州は高遠の地に引っ張りだすことに成功したわけであります。
なぜ、高遠か?
という質問をするような失敬な輩に対しては
”武田信玄のカブトをかぶりながら、
風林火山の置物をその絶壁の頭にこすりつけ、
頭がベートーベンのような髪型になるまで回転せざるを得ないのであります。”
高遠といえば
仁科盛信公(にしなもりのぶ こう)
であります。
これはセンター試験に毎年出る問題であり、
我々は呼び捨て出来ないがために
御君仁科盛信公
と書かざるを得ず、☓とされるのが武田信玄研究家にとっての常でございます。
武田信玄については経営者の学問としてもはや必須項目であります。
祇園精舎の鐘の声諸行無常の響きあり
(ぎおんしょうじゃのかねのこえ しょぎょうむじょうのひびきあり)
まさにこの言葉がぴったりであります。
孫子を地で行く信玄は
兵は詭道なり(戦いはだまし合いである)
との言葉通り
権謀術数を繰り返し、力の劣る信州の小大名を切り従え、日ノ本7州にまたがる太守となったまでは良いものの
その晩年は迷走してしまいました。
また死後は後継者武田勝頼が長篠の戦いにおいて12,000の精鋭を
あるみ谷に待ち構える織田・徳川連合軍の35,000の陣地要塞(つまり即席の城)に突撃することで
そこから
衰運の一途をたどることとなります。
この突撃に関しては信玄時代を築いた侍大将達がみな死地を得たと感じたのではないかと解釈できます。
信玄の時代は良かったと昔を懐古しながら自ら死地を得た格好があります。
自らの死をもって半ばやけくそになって勝頼を
諫めた。そんな悲しい思いが漂います。
歴史の解釈で大きく異なるのは、この長篠の戦いであります。
当時武田勝頼は最大版図で数か国の太守でありました。
一方信長も毛利と敵対し、かつこの武田勝頼との対決においては、
信長が弱者のような解釈が一般的であり、
強者 武田 対 弱者 織田
信長の新しい戦術、三段撃ちによって戦術的に勝利した。  ※馬防柵
※馬防柵
という理解が一般論でありますが、
まったく異なります。
というのは、当時信長は伸び盛り、
肥沃な濃尾平野(美濃・尾張・伊勢)をすべて抑え、当時の先進地域であった近江をも抑え、上洛により
足利将軍家の威光を盾に肥沃な畿内を平定しています。
日ノ本の3大平野のうち濃尾平野と関西平野をすでに抑えており、石高600万国、動員兵力
20万を超えております。
ここに忠実な同盟国の徳川家康30万国をあわせ日ノ本一の列強国でありました。
かたや武田は面積はひろいものの、
狭隘な甲府盆地、山間の信州が中心で
最大石高120万国動員兵力3万6千であります。
つまり当時の規模においては
武田信玄が上杉謙信と川中島でごちゃごちゃやっている間に
織田信長が西国攻略に力を集中でき、大きく差が開いてしまったというわけです。
信玄在陣中、この間信長は信玄に対し常に土下座外交をしているということで
戦いをしかけることはありませんでした。
”兵は勝ち易きにかつものなり”
という理論を忠実に実行していたのはむしろ信長の方であったというのが正しい解釈になります。
武田に対して常に贈り物を届けていたと言われる
かの信長が信玄を心から尊敬していたなどということは考えづらく、
土下座外交の裏にある意図が見え隠れしていてとてもおもしろいです。
勝頼の代になるとすでに織田と武田の力の差は開くばかりで時間を追えばその差は更に歴然としてくることが明白だったということです。
強者 織田 対 弱者 武田
という図式が成り立ちます。
つまり事、ここに至っては
乾坤一擲の決戦において早めに雌雄を決すべきというのは、むしろ武田勝頼の方であり、
この焦りを利用して陣地要塞(臨時の城)に誘いこんだ信長の戦略的勝利と言えると思います。
こうして長篠の戦いは運命を回転させていくわけです。
馬場信春、山県昌景、内藤昌豊、原昌胤(まさたね)、真田信綱、真田昌輝、土屋昌次
といった歴戦の侍大将たちを失いました。
古参の侍大将のほとんどを失い、勝頼にとってはうるさい家臣たちはいなくなったものの
ただでさえ少ない兵力、機動力をそがれることになりました。
ただ、実は長篠の戦い、その後は坂道を転げ落ちるよう・・・というわけでもありません。
ここからおどろくべきことに7年の間なんとか持ちこたえています。
これは無き信玄公の威光でしょう。
周辺の列強は武田が衰えたりといえども無理やり攻め入ってやけどすることを相当恐れているということです。
ここから立て直す事もできたかもしれませんが、ここで致命的な外交的失敗をします。
きっかけは信玄のライバル上杉謙信の死であります。
謙信には妻がおらず、代わりに二人の養子が存在していました。
1人は姉の子、甥の上杉景勝、
もう一人は
関東の北条氏政の子、上杉景虎です。
越後は景勝と景虎派に別れ、激しい内乱が起こります。
世に言う”御館の乱”です。
当時北条と同盟していた武田勝頼は上杉の本城春日山城に向けて進撃中でありました。
北条は当然上杉景虎を擁立しようとするわけで、景勝としては四面楚歌の状態に陥りました。
ここで景勝派は勝頼に対し、北信濃の一部と東上野、さらに黄金一万両をもって調略します。
勝頼とすればここで北条と上杉(景虎)が同盟すればいずれ後年の敵となると想定し、この条件を受け入れます。
景勝は景虎を御館に攻め、結局上杉は景勝派が勝利を収めます。
※景勝派に直江山城守兼続がいたということです。
この上杉景勝側に着くという行為は、北条の遠交近攻策により結局北条の後ろ盾を欠くこととなります。
外交的失敗により、東の後北条、西の織田、南の徳川という連合国を相手に戦わなくてはならなくなりました。
なにやら旧日本軍とダブって見えてしまいます。
やっとの思いで取った堅城、高天神城がついに徳川に取られたこと、
岩村城も織田信忠に取られたことが相当大きい影響がありました。
とくに両城に関しては後詰(援軍)をしなかった。(できなかった。間に合わなかった。が正しいです。)
ことが内部の諸将のただでさえ不安な精神状況に激震を与えたことは想像に硬くありません。
武田家の家臣群からすれば
こう思ったことでしょう。
”我々の領土に敵が攻め入った場合、
もはや後詰はこない”
と。
版図が大きく成るに従い、信長は地方軍団性に移行し、各方面軍団長にその任を与えています。
会社組織でも同じですよね。
しかし武田軍の場合、山奥の甲府から本軍を集めて行軍するため極めて機動性に欠けます。
また長駆移動の弊害が多々あり、厭戦気分が蔓延していたと言います。
遂には織田の武田征伐において
内憂外患ともうしますが、
木曽義昌が木曽谷をすべて明け渡し、典厩信豊、穴山梅雪といった一門衆(親類)からも裏切られてしまいます。
もともと勝頼は正式な跡目ではなく、信玄の孫の信勝の後見人という立場でありました。
これでは諸将をまとめる事、特に一門衆の扱いには相当苦労したのであろうことは想像に難くありません。
最期はいち早く新府城を捨て、小山田信茂を頼って甲府の東、天然の要害、
岩殿城(いわどのじょう)へ向かうものの、
なんとこちらでも裏切られ、
行き場をなくした武田勝頼主従はひたすら山中、北に向かいます。
戦わずして僅か40名となり
薄暗い
天目山の山中でその生涯を閉じることとなります。
どこに高遠が出てきたんや!?
という話については、
このような衰運をたどった武田家の晩年をまず理解する必要があります。
その上で
一門、普代衆が続々と裏切るなか、
木曽谷の攻略、南信攻略で意気上がる織田信忠、滝川一益の連合軍は30,000とも50,000とも言われる大軍勢を率いて
伊那の要衝高遠に的を絞ります。
ここが落ちれば杖突峠を通って、諏訪、そして甲府攻略は目と鼻の先です。
新府城は普請中であり、高遠が落ちれば、故郷の諏訪が蹂躙され、そこから甲府が落ちるのは時間の問題です。
ここに及んで
城将、仁科盛信公(勝頼の弟にあたります)は
僅か3,000の兵をもって、この大軍を迎え撃つことを決断します。
武田本隊がこの堅城に兵力を集中配備出来なかったのは、各方面の裏切りを警戒するものと徳川が南、北条が西から続々と押し寄せて来ているためです。
さて高遠は如何に堅城といえども十倍以上の大群を引き受け、四方八方から敵が押し寄せる状態にあり、本軍の後詰が絶望的な状況であります。
やがて織田信忠の総攻撃の号令がなされ、
西門、北門、南門、そして搦手方面と四周から十倍を超える兵力が本丸に向けて突撃してきます。
織田方にすれば、すでに勝敗が決している以上、如何に大将首を取るか、これにかかっているわけで、
しかも相手は武田勝頼の弟。
織田の軍勢の士気は天をつくばかりであったことでしょう。
天然の堀である川をわたって続々と押し寄せる織田の大軍に
死を覚悟した仁科隊は死兵をもって戦うも
負けはすでに見えています。
兵力の少ない敵に対しては、包囲進撃が有効です。
全周から織田軍は押し寄せます。
やがてがけを登り、曲輪群が落ち始めました。
四周から押し寄せる敵軍の中、
仁科盛信はもはやこれまでと死を覚悟したことでしょう。
自らの臓腑を壁に叩きつけながら壮絶な最期を遂げます。
この26歳の青年が叩きつけた怒りというのは、織田や信長への怒りではなく、
不甲斐ない譜代や裏切る一門衆に向けてのものだったような気がしてなりません。
衆寡敵せず敗れ去ったものの、
その最期は地元に今でも語り継がれ、
今は平和を象徴する桜の山城として全国各地からたくさん人が押し寄せているのです。
それがこの高遠という地なのであります。