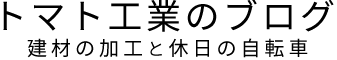【断言】トヨタと日本車が中華EVに負けないと思う「5つの理由」
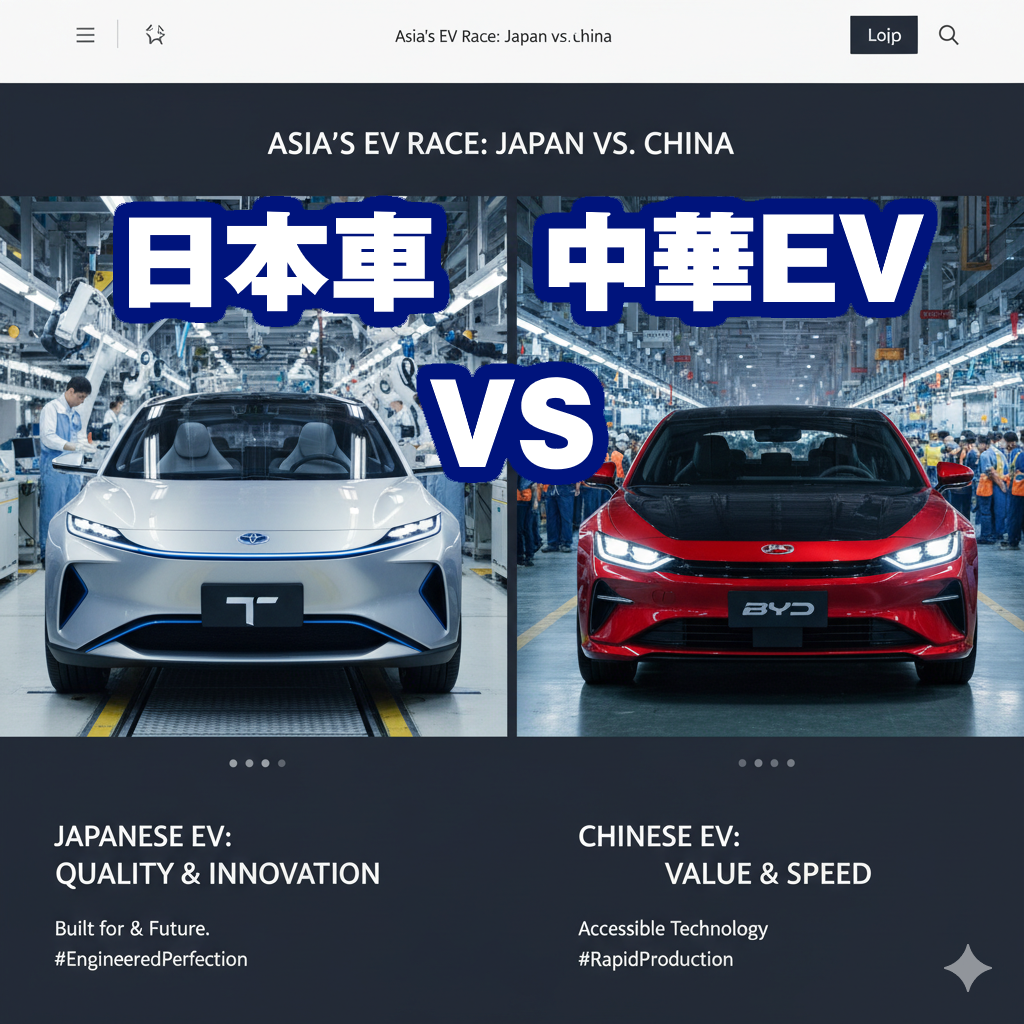
メディアは「中国EVが安い、進んでる❢」と騒ぎ、
日本車は遅れていると言います。
本当にそうでしょうか?
ものづくり会社の代表としてどう考えるかを、ここにはっきり明示していきたいと思います。
先に言いますと、弊社トヨタや車メーカーとは大きな取引がありませんので、
この記事を書くことになんにもメリットがありません。
また、中華サイトから気持ち悪いメールがくるだけです。
特に、東南アジア諸国など人口が増加している有望な主戦場を
BYDなど中華EVに取られてしまうのではないか?
という視点がよく叫ばれています。
結論、”負けない”と考えています。
以下理由になります。
フィリピンで見た実際
フィリピンのニノイ・アキノ国際空港で、いきなりボッタクリタクシーにあった私ですが、
グラブタクシーというタクシーアプリで、マニラやセブでタクシーを使い倒しました。
その時に現地タクシードライバーさんと会話するわけです。
私が、
「なぜ日本車しか乗らないの?EVは?」
と聞くと、
彼らは決まってこう言いました。
「お前は日本車の良さがわからないのか。
EVなんか乗るわけ無いだろ。
俺達はプロで、車は稼ぐための道具だ。
そもそもこっちは毎日事故が発生するんだが、

日本車は故障しないし、故障してもすぐに直せるし、部品も安い。
だから俺達は日本車しか乗らないんだ!」
と嬉しそうに胸をはっていました。
たとえば東南アジアの多くの道路は、
大きな穴(ポットホール)や段差、未舗装路、冠水、
そしてひどい渋滞が慢性化してます。

車だけでなく、バス、トゥクトゥク、歩行者、バイク、原付き、自転車
それに犬までいます。
急加速、急発進、段差、穴、砂、石、水、泥、湿気・・・
故障や事故の原因だらけなんですよね。
この環境で求められるのは、車の「信頼性」です。
日本車は耐久性が高いためそもそも故障が少ないですが、
もし壊れても、部品が現地に豊富にあり、町の小さな整備工場で安く、すぐに直せるのが強みです。
一方、中華EVは購入時の安さやスペックが魅力ですが、
高額なモジュール交換が必要になるリスクがあります。
部品供給が滞れば、修理に数週間〜数ヶ月も車が使えないリスクがあります。
中国企業が儲からない修理部材なんか取り扱わないことは、
すでに建築業界では有名です。※後述しますが。
【発火、火災、爆発注意!!】【純正と互換バッテリーの違いとは?】マキタ純正バッテリーと互換バッテリーの真の違いとは?実際に分解してみたよ。
仕事で使うプロにとって、「壊れたら待つ時間」は稼げない損失であり、
車の安さなどすぐに吹き飛びます。
なぜ、壊れないのか、そして壊れたときの対応にどのような思想が込められているのでしょうか?
そこには決定的な”思想”の違いがあります。
設計哲学の根本的な違い:「修理」か「交換」か
この現場での信頼性を生んでいるのが、日本と中国EVメーカーの設計思想の根本的な違いです。
日本車:「壊れ方」まで設計する現場の哲学
日本製品の設計思想は、「長く使ってもらうこと」が前提です。
生産技術的にいうと、以下の特徴があります。
- 規格の統一: ネジやボルトは国際標準(メートル規格)が徹底されています。
世界中どこへ行っても、その地域の標準的な工具で修理ができます。ちなみに、アメリカでよく使うインチネジは、整備士にとっては、ミサイルを打ち込みたくなる規格です。
整備のことを設計段階から考えて国際標準規格を採用する。ボルトの長さもできるだけ揃える。
これこそ、おもてなしの思想ではないでしょうか。これを無意識で行ってるってことです。 - 折損の思想: 最も重要な部品(車軸、バッテリーパックなど)を守るため、あえて交換しやすい安価な部品に「破損の起点」を作っておきます。大きな衝撃を受けたとき、この「ヒューズ」のような交換可能な部品が身代わりになって壊れることで、高額な主要部分へのダメージを防いでくれます。
これも日本の機械や部品の大きな特徴です。全体をガチガチにしてしまうことをしません。 - 整備前提の交換思想: 部品を細かく分け、整備士が少ない工具と最短の時間で交換できるよう設計します。整備士の作業効率を高め、修理コストを下げます。テスラのギガプレスは初期コストは安くはなりますが、修理時には全交換が必要になってしまいます。
では、中華設計思想といういのはどういう思想でしょうか?
【発火、火災、爆発注意!!】【純正と互換バッテリーの違いとは?】マキタ純正バッテリーと互換バッテリーの真の違いとは?実際に分解してみたよ。
※参考ブログ
中華EV:「技術保護」と「高統合化」の思想
中国EVメーカーは、コスト削減と技術の保護(コピー対策)を優先します。
日本が増税仕放題文化だとしたら、
あちらはコピー文化、さらに、激しい価格競争で、他社に模倣されないよう、
独自規格のボルトを乱用します。
また、とにかく部品には安さを求めます。
たとえば、日本の製品であれば、なるべくサイズを統一しようとするのですが、
中華製品の場合、なるべく細くて小さい、安いボルトにしようとします。
つまり、同じ製品の中に複数のボルトナットが混在しやすくなります。
また、多くの機能を一つのコンピューターにまとめたECU(車版CPU)というのがあるのですが、
こうした制御をブラックボックス化します。
結果、故障してもメーカー専用の診断機がなければ原因が特定できず、
高額なユニット全体の交換を強いられることになります。
これは、「安く買って、高く治す」という状況になりやすいことを意味します。
実際に、本国でもBYDの多くのディーラーが閉店(済南乾城汽車貿易)しています。
整備性については、独自規格のボルトやナットが散発されると整備性が劣る他、
復旧までに時間がかかって修理コストもかかります。
顧客満足度の低下した車をリピートしようと思うでしょうか。
ECUのブラックボックス化は日本車でもそうはそうなのですが、中国の場合は、それが顕著です。
おそらくですが、コピー文化から身を守るためではなかろうかと考えています。
”いや、そんなこと言ったって結局は安いものが売れるだろうが。”
って声もあると思います。
歴史の教訓:高性能よりも信頼性が勝敗を決める
この「カタログスペック vs 現場の信頼性」の勝負は、
実は歴史が何度も繰り返してきた教訓です。
日本の隼と飛燕の例
第二次世界大戦で、
日本軍の一式戦闘機 隼 は、ドイツ設計の水冷エンジンを積んだ
高性能三式戦闘機 飛燕 よりも、現場で愛されました。
その理由は、構造が単純で整備が容易だったためです。
現場では常に高い稼働率を維持できました。
一方、カタログスペックでは高性能な飛燕は、
複雑で繊細なエンジンゆえに整備が難しく、現場の信頼を失いました。
野球でも、故障しがちなガラスのピッチャーよりも、
毎日動けるピッチャーの方が監督としてはありがたいですよね。

三式戦闘機も、3,000機も生産されましたが、めだった活躍はできていません。
タイガー戦車の例
海外で同じような例はなかったのでしょうか。
ドイツの重戦車 タイガー戦車は、

その圧倒的な火力と装甲を持ちながら、重すぎる車重と、複雑な設計のためにトランスミッションや
キャタピラーの故障が多く、
前線での稼働率が非常に低かったことが知られています。
現場では信頼性が高く、整備性が良い四号戦車が好まれました。
マキタの例
いやいや、まぶちよ、そんな80年も前の話したって参考にならないだろ!!
って声があるかもしれません。
では、現代ではどうでしょうか?
日本では一時期、ホームセンターで売られる安価な電動工具がプロの建設現場にも出回りました。
しかし、
”こんなもん使えないな。”
という評価に落ち着き、
今も現場に残っているのはマキタやHIKOKI(日立)の製品に集約されています。
今、
ちゃんとしたプロでこれら道具を使ってない人を私は知りません。
プロはそんなもの使わないってことです。
その理由は、仕事中に工具が壊れたときの損害(工期の遅れ、人件費)
が、工具本体の価格差を遥かに上回るからです。
また、ホームセンターの電動工具は修理不可でDIY向けの消耗品になります。
壊れたら、修理部品なんかあてにせず、捨てて新しいのさっさと買ってください。
の世界です。
電動工具を毎日使うプロは、結局どちらがお得であるかを知っています。
このように、プロの道具には「途中で壊れない信頼性や整備性」が必要なのです。
車に置き換えると、もし仮に、大事な会合やパーティがあったとすると、
1%の確率で壊れるかもしれない車
と
壊れない車。
どちらの車に乗りますか?って話だと思います。
大事な案件であればあるほど、後者を選ぶはずです。
たった一度であっても、残念な経験をしたのならば、
次からそのメーカーの車に乗ろうなんて思わないはずです。
現代のEVも同じです。
カタログ上、たとえ高性能で安く見えても、
現場で稼働し続けなければ意味がありません。
EV時代において、トヨタをはじめとする日本車が持つ
「壊れにくさ」「安心できる共通規格化」「現場を裏切らない設計思想」「整備設計思想」
こそが、世界市場で圧倒的な信頼を勝ち取り、
最終的な勝者となると私は思います。
それでも今は、東南アジアでは中華ゴミEV(あえてゴミと形容します。)
が溢れかえっています。
今はいっとき、ホームセンターの格安電動工具が日本中の建築現場に出回ったように、
EVが席巻したとしても、
これを耐えれば一周回って日本車の良さが再評価される時代が必ず来る。
と私は思います。
みなさんは、どう考え、感じますでしょうか?